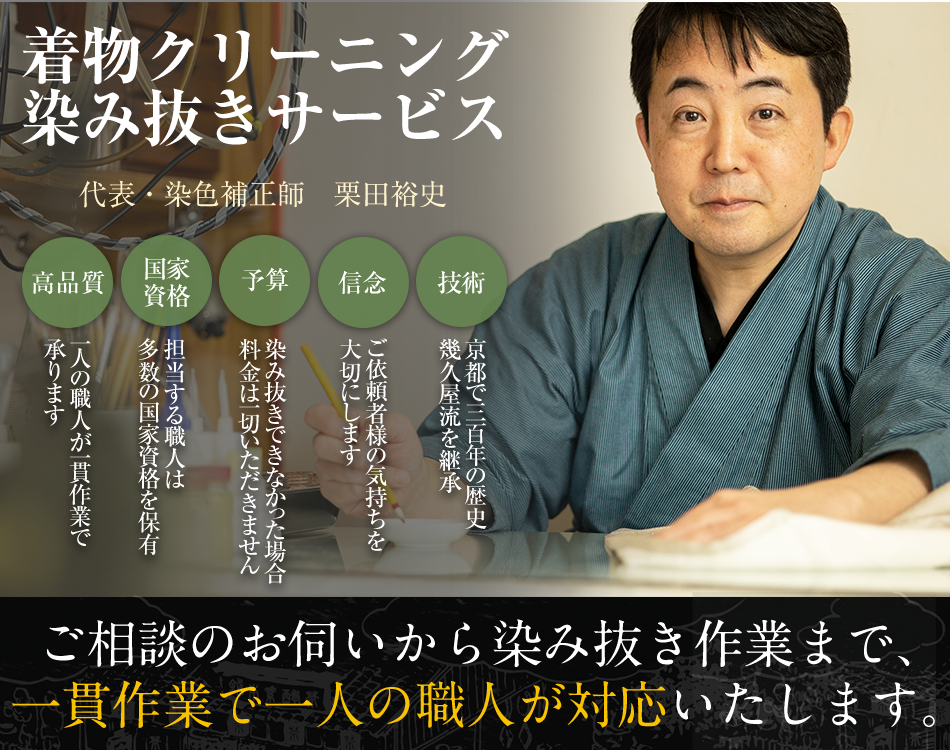宮廷のおしゃれと「着物のお手入れ」の深い意味
奈良時代や平安時代は、今につながる日本の「着るもの文化」が始まった、とても大切な時代です。特に平安時代になると、身分の高い貴族たちが身につける豪華な衣装は、その人の社会的な地位や、どれだけ教養があるかを示す、大切な手段となりました。
この頃から、「着物をきれいに保つ」とか「きちんと整える」という行動が、単に汚れを落とすだけでなく、心のあり方や、特別な儀式のような、もっと深い意味を持つようになったんです。
当時の貴族が着ていた服といえば、たとえば「狩衣(かりぎぬ)」や「袿(うちぎ)」、そして何枚も重ねて着る「十二単(じゅうにひとえ)」といったものが挙げられます。これらは、絹(シルク)でできていて、とても繊細で高価なものでした。だから、今の私たちのように頻繁に水でゴシゴシ洗うなんてことは、まずありませんでした。むしろ、「洗う」という考え方そのものが、今の時代とは全く違っていたと言っていいでしょう。
着物の清潔さ = 「悪いものを追い払う」おまじない?
当時の日本の社会では、「汚れ」というのは、ただの物理的なホコリやシミのことだけではありませんでした。宗教的にも、そして精神的にも「汚れたもの」「不浄なもの」だと考えられていたんです。特に、日本の神様を大切にする「神道(しんとう)」の考え方では、「穢れ(けがれ)」という、不幸や不運をもたらすような悪いものをとても嫌いました。だから、その「穢れ」を追い払うための儀式や、昔からの習慣が、日々の暮らしの中にたくさん取り入れられていたんです。
例えば、大きな災難を避けるための「大祓(おおはらえ)」という儀式では、自分の身に降りかかった悪いもの(穢れ)を、着物に乗り移らせて清める、ということが行われていました。人の体にまとわりついた穢れを服に移し、その服を川に流して清める、という考え方ですね。これは、着物が単なる「モノ」ではなく、人の心の状態や運命に深く関わる、特別な存在として見られていたことを物語っています。
着物を洗うより「干す」「お香を焚く」が大事だった
平安時代の貴族の衣装のお手入れで、最も重要だったのは、水で「洗う」ことではありませんでした。むしろ、「干す(ほす)」ことや、「薫(た)く」(お香を焚いて香りを移す)ことが中心だったんです。
例えば、平安時代の有名な随筆『枕草子(まくらのそうし)』には、干している着物や、風になびく着物の様子が、とても美しく描かれています。これは、単に「実用的な行動」だっただけでなく、季節の美しさや、上品な風情を表現する文化的な象徴としても、とても大切にされていた証拠です。
また、着物にお香を焚き染めて、良い香りを移す文化も深く根付いていました。着物から漂う香りは、身だしなみを整えるだけでなく、その人の自己表現の一部でもありました。どんな香りのセンスを持っているかで、その人の教養や育ちが良いかどうかが判断されたほどなんです。つまり、着物のお手入れは、当時の人の生活様式や、人との関係性にまで深く影響を与えていたんですね。
「洗い張り」のルーツ? — バラしてから洗う技術の始まり
平安時代に行われていた着物の洗い方は、今の私たちのように、水と石鹸でもみ洗いするようなものではありませんでした。特に絹のような高級な素材は、水に濡らしただけで風合い(手触りや見た目)が損なわれてしまうため、非常に慎重な扱いが求められました。
この頃の「洗い」に近いお手入れとしては、着物を一度ほどいて、一枚の平らな反物(たんもの:着物の形になる前の長い布)の状態に戻してから干す、という方法が使われていた可能性があります。これは、今の「洗い張り」という技術の原型(もと)とも言えるでしょう。当時の詳しい技術の記録はあまり残っていませんが、「着物を反物の状態に戻して整える」という考え方は、この平安時代にはすでに始まっていたと考えられています。
貴族社会と「女房装束」の管理:おしゃれと日々の務め
平安時代の貴族の女性たちにとって、自分の衣装をどのように管理するかは、とても大切なことでした。特に、天皇のいる宮中で働く「女房(にょうぼう)」と呼ばれる女性たちは、常に身なりを美しく整えておくことが求められ、衣装のお手入れも、日々の大切な仕事の一つとされていました。
また、女房たちの間では、衣装の貸し借りも日常的に行われていたそうです。そのため、「誰がどんな服を持っていて、どんな良い香りが服に移っているか」といったことが、貴族たちの社交の場で話題になることもあったと言われています。着物のお手入れが、コミュニケーションの一部にもなっていたのですね。
庶民の暮らしと着物のお手入れ:麻や木綿、そしてシンプルな洗い方
身分の高い貴族たちが絹を中心とした豪華な着物をまとっていた一方で、庶民の衣服は、麻(あさ)や葛(くず)といった植物の繊維でできたものが主流でした。これらの素材は比較的丈夫で、水洗いにも耐えることができました。
そのため、農民や職人たちは、川や井戸で衣服をゴシゴシと手洗いする文化がありました。このような洗い方は、厳密には貴族の「クリーニング」というよりも、今の「洗濯」に近いもので、洗い張りや香を焚き染めるといった文化的な側面は、あまり見られませんでした。
しかし、日々の暮らしの中で自分の衣服を清潔に保つことは、やはり基本的な衛生の考え方として重要でした。「着物に気を遣う」という意識は、身分にかかわらず、多くの人に共有されていたのです。
時代を超えて受け継がれた「洗わないお手入れ」の心
奈良時代から平安時代にかけての着物のお手入れを見てみると、この時代には「洗う」ことよりも、「着物を美しく整える」ということが一番大切にされていたことがよくわかります。
- 着物にお香を焚いて、良い香りを移す。
- 着物を風に当てて、湿気を取り、スッキリさせる。
- シワを伸ばして、いつも美しく保つ。
- 単なる汚れではなく、「穢れ」を払う目的でお手入れをする。
- 周りの人への気配りや、人間関係を表現する「衣のおもてなし」。
こうした行動は、今の「着物クリーニング」にも通じるものがあります。単なる作業ではなく、「美しさへのこだわり」や「精神性」が、そこには込められていたんですね。
まとめ:平安貴族が作った「着物のお作法」が、今の技術の始まり
奈良・平安時代に育まれた「着物の扱い方」は、その後の時代にも強い影響を与えました。そして、日本の染め物や織物の文化、着物のお手入れを専門とする「悉皆(しっかい)」の文化、さらには現代に続く着物クリーニングの技術の「心の土台」となっています。
着物を単なる「道具」としてではなく、「良い気を通すもの」や「心を映し出すもの」として扱ってきた日本人の繊細な感性は、今でも、長く続く老舗のクリーニング職人さんたちの丁寧な仕事ぶりや、言葉の端々から感じ取ることができます。
次の章では、この「着物を大切にする心」が、どのように江戸時代の商人文化や、庶民の暮らしの中に受け継がれていき、より実用的で技術的なお手入れ方法へと進化していったのかを、さらに詳しく見ていきましょう。