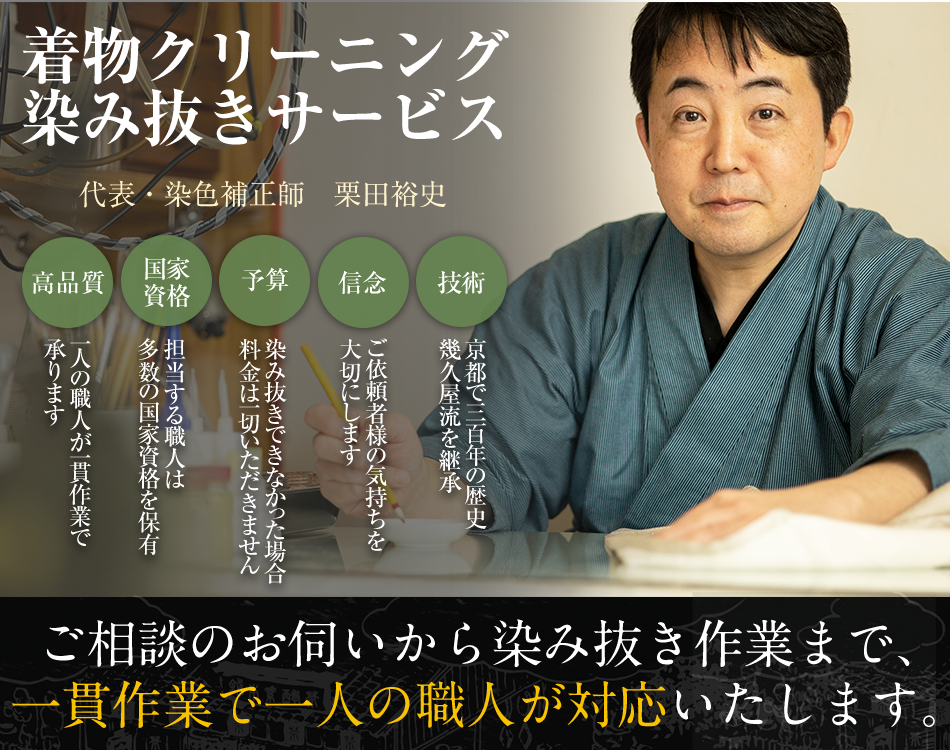「文明開化」とともにやってきた、「洋服ブーム」の波
明治時代が始まると、日本は国を大きく変える、まさに大転換期を迎えました。江戸時代が終わり、鎖国を解いて外国と交流が始まった激動の時代に、「脱亜入欧(だつあにゅうおう)」(アジアを抜け出し、ヨーロッパに学ぶ)というスローガンのもと、私たちの暮らしのあらゆる面が、西洋の文化から大きな影響を受けることになったのです。
1871年には、男性が髪を短くする「断髪令(だんぱつれい)」が出され、その翌年には「洋服を役所の制服にする」という命令が出ました。これにより、侍のちょんまげや着物姿はあっという間に減り、役人さんや軍人さんは、スーツや軍服を着るようになっていきました。
しかし、このように急速に洋服が広まっていったにもかかわらず、ふつうの人々の生活では、まだまだ着物が主流でした。そのため、「着物を洗う」「お手入れする」という、古くからの文化は、すぐに消えてしまうことはありませんでした。
着物と洋服の「共存」 — 暮らしの変化が生んだ、お手入れの「分業」
明治時代から大正時代にかけては、多くの人々が「外に出る時は洋服、家の中では着物」というスタイルで生活するようになりました。まるで、二つの違う生活を送るような形です。
- 洋服の場合:特に都市部に住む男性を中心に、洋服を着る人が増えました。これに合わせて、洋服を専門に洗う「クリーニング業者」が新しく登場し、発展していきました。
- 着物の場合:着物は、家で着る服として定着し、江戸時代から続いてきた伝統的なお手入れ方法が、引き続き行われていました。
この結果、「洋服はクリーニング屋さんに出すもの」「着物はお馴染みの悉皆屋さんにお願いするもの」というように、着物と洋服のお手入れが、それぞれ別の専門家によって行われる「分業体制」が社会に根付き始めたのです。
職人の技が「ビジネス」に — 着物のお手入れが「産業」へと変化
江戸時代には、職人さん個人の高い技術や経験に頼っていた着物のお手入れが、明治・大正時代になると、都市の人口が増えたことで、「仕事」としての需要が大きく増えました。
明治20年代(1887年頃〜)には、一人ではなく、たくさんの職人さんを抱える「業者」が現れるようになりました。これによって、着物のお手入れの方法にも、次のような変化が生まれていったのです。
- 料金がハッキリして、サービスの質が一定になった:これまでは職人さんによってまちまちだった料金や技術が、より分かりやすく、誰にでも安心して頼めるようになりました。
- お店の受付窓口ができた:お客様が気軽に相談したり、着物を預けたりできる場所ができました。
- 遠い地方からの注文にも対応できるようになった:郵送サービスが始まったことで、遠くに住む人も着物のお手入れを依頼できるようになりました。
- お手入れの工程を分担するようになった:例えば、「シミ抜き専門」「洗い専門」のように、工程ごとに職人が分かれて作業するようになり、効率が上がりました。
新しい素材と化学染料の登場 — 着物の洗い方に大きな変化!
明治時代も終わり頃になると、ヨーロッパからアニリン染料という新しい化学染料や、人造絹糸(じんぞうけんし)という、本物の絹に似せて作られた新しい糸が登場しました。これらは、着物の色や素材に多様性をもたらした一方で、着物の洗い方に新たな難しい問題を生み出すことになります。
- 化学染料:水や摩擦に弱く、色落ちしやすいものがありました。
- 人造繊維:熱や特定の薬剤に弱く、縮んだり溶けたりすることがありました。
- 柄の復元:新しい染料や素材を使った着物のシミ抜きや補修には、より高度な技術が必要になりました。
着物職人たちは、これらの新しい素材や染料に対応するため、化学の知識や温度管理の技術など、これまでの経験に加え、新しい知識を積極的に取り入れ、自分たちの技術をさらに進化させていきました。
女性たちと「洗い張り」文化が家庭に広まった時代
この時代、女性たちは家庭で「洗い張り」の方法を学び、「家族の着物を守る、大切な心遣い」として、着物のお手入れ文化をしっかりと次の世代へと伝えていきました。
特に農村部では、冬になると家族みんなで協力して「張り場」(洗い張りをする場所)を作るなど、洗い張りが一年間の行事の一つとなっている地域もありました。それは、着物が単なる服ではなく、家族の暮らしに深く根ざした大切なものだった証拠です。
しかし、都市部では、次第に「洗い張りは専門業者に出すもの」という考え方が強まり、家庭で着物を手入れする文化は、少しずつ衰退していってしまいます。
シミ抜き技術の進化と「しみ抜き屋さん」の誕生
着物の「染み抜き(しみぬき)」の技術は、この頃、化学の知識と結びつくことで、さらに進化し始めました。
アンモニア水やアルコール、さまざまな種類の漂白剤などを使う技術が登場し、着物の大切な色を守りながら、シミだけをきれいに落とす方法がどんどん発展していきました。
この時期に、シミ抜きに特化した「しみ抜き屋」という専門職が現れ、これが現代の「シミ抜き専門店」の原型(もと)となっていきます。
着物文化の「分かれ道」 — 洋服時代の到来と、着物の選び方
大正時代も終わりが近づくと、着物は、もはや普段着ではなく、「特別な日に着るおしゃれ着」として扱われるようになりました。
- 学校では、学生服やセーラー服が広く着られるようになった。
- 女性たちが社会に出て働く機会が増え、洋服を着る人が増えた。
- 百貨店などで洋服がたくさん売られるようになった。
このように、毎日の生活の中で着物を着る文化は少しずつ衰退していきました。呉服店や悉皆屋さんも、お正月や結婚式、七五三といった「特別な儀式」で着物を必要とする人たちの需要に応える形で、なんとか商売を続けていったのです。
まとめ:近代化の波の中で、着物とクリーニングはどう生き残ったか
明治・大正時代の近代化という大きな変化の中で、着物のお手入れ文化は様々な影響を受けました。
- 着物のお手入れが、個人の技から「ビジネス」へと再編されたこと。
- 新しい素材や化学染料に対応するため、技術がさらに高度になったこと。
- 都市部では、家庭で着物をお手入れする文化が減っていったこと。
- 着物が、「普段着」から「特別な日に着る服」へと役割を変えたこと。
- シミ抜きや修理といった、着物を再生させるための大切な技術が、次の世代へとしっかりと受け継がれていったこと。
近代化の大きな波が押し寄せる中でも、職人さんたちの知恵と、着物を大切にするお客様の信頼によって、着物とそのお手入れ文化は生き残り、形を変えながらも現代へとつながっていったのです。
—
この章で、明治・大正時代の着物のお手入れ事情が少し見えてきましたね。皆さんは、この時代の変化についてどう感じますか?