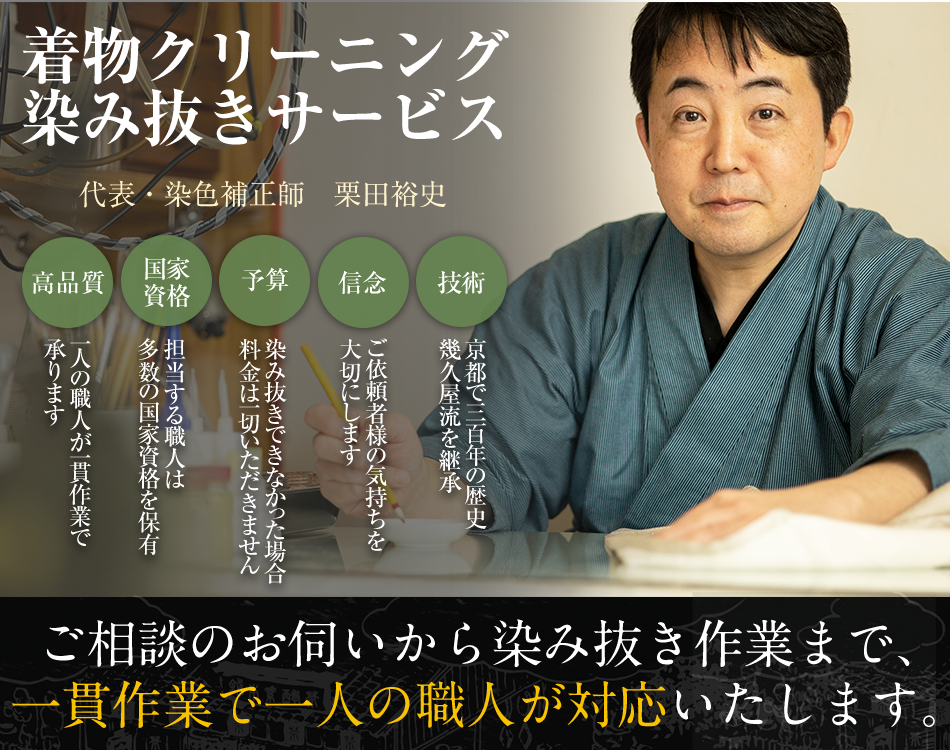高度経済成長期 — 洋服が当たり前になった社会の、すさまじいスピード
昭和の時代、特に第二次世界大戦が終わって日本が復興し、経済がめざましく発展した「高度経済成長期」(だいたい1950年代から1970年代にかけて)は、「なんでもたくさん作って、たくさん消費する社会」がものすごい勢いで形作られていきました。
この時代、洋服は単なる「外来の服」というだけでなく、おしゃれを楽しむための「ファッション」として、すっかり私たちの生活に定着しました。それに加えて、プラスチック製品や、ポリエステルなどの「合成繊維」がどんどん普及したことで、服はまるで「使い捨ての時代」に突入したかのようでした。今の「ユニクロ」の前身となるような、気軽に買えるカジュアルな洋服ブランドも、この時代にどんどん広がり、多くの人々にとって「着るものといえば洋服」という価値観が、当たり前になったのです。
このような大きな変化の中で、人々が着物にかけるお金や、着物に対する意識は、劇的に下がっていきました。普段着として着物を着る姿は、日々の生活からほとんど見かけなくなり、着物は結婚式やお葬式、成人式など、「特別な日」にだけ着る、めったに着ない服へと変わっていったのです。
クリーニングの需要も、洋服向けの洗濯やクリーニングへと大きく移っていきました。その結果、着物のお手入れを専門に行う職人さんや、悉皆屋(しっかいや)さんも、残念ながら次第に数を減らしていくことになります。着物文化にとっては、まさに「冬の時代」の始まりでした。
安くて大量の洋服 — なぜ日本人は「着物を着なくなった」の?
合成繊維は、丈夫でシワになりにくく、しかも大量に安く作ることができました。さらに、海外から輸入される安い洋服も増え、洋服は誰でも手軽に買えるものになっていきました。1964年の東京オリンピックを境に、日本の経済はさらに加速し、デパートやファッションビル、そしてスーパーや量販店が日本中に次々とオープンしました。
また、一般の家庭でも、洗濯機や家庭用の乾燥機が買えるようになり、毎日のお洗濯は、わざわざクリーニング店に行かなくても、家の中で簡単に済ませられるようになったのです。
このような大きな時代の流れの中で、着物は、お手入れに手間も費用もかかる「高級品」、あるいは「とっておきのおしゃれ着」という特別な位置づけになっていきました。その結果、着物を着る機会そのものが減り、それに伴って、着物の「洗い」や「お手入れ」を専門家に依頼する文化も、大きく縮小していったのです。
昔は、着物一枚を大切に何十年も着続け、親から子へと受け継ぐのが当たり前でした。しかし、この時代からは、流行に合わせて新しい洋服を次々と購入し、古くなったら捨てるという「使い捨て」の考え方が主流になります。着物の持つ「長く大切にする」という価値観は、人々の意識の中から少しずつ薄れていったのです。
例えば、かつては家々に必ずあった「桐(きり)ダンス」も、洋服が増えるにつれて「洋服ダンス」に置き換わっていきました。着物を収納するスペースさえもが、家庭から姿を消していったのです。これは、単に収納家具の変化というだけでなく、着物が日々の生活から遠ざかっていった、象徴的な出来事とも言えるでしょう。
家庭での着物お手入れの「終わり」と、専門家の減少
昭和の時代には、日本の家族の形も大きく変わりました。大家族から、お父さん、お母さん、子どもたちだけの「核家族(かくかぞく)」が主流になっていったのです。昔の大家族では、おばあちゃんやお母さんが、嫁入り道具として持たされた着物や、親から譲り受けた着物を、家でほどいて「洗い張り」を行うのが当たり前でした。しかし、核家族化が進み、そのような知識や技術を受け継ぐ環境は激減してしまいました。
さらに、若者たちが仕事を求めて都市へと集中し、夫婦共働き(夫婦が共に外で働く)の家庭が増えたことで、家庭の中で着物をお手入れする文化は、ほとんど消えてしまったと言ってもいいでしょう。それに伴い、悉皆屋(しっかいや)さんや、染み抜き職人さんといった、着物の専門家への依頼もどんどん減っていきました。
その結果、昔はどの町にもあった地域密着型の悉皆屋さんは、廃業(お店を閉めること)したり、業務を縮小せざるを得なくなったりしていきました。町の着物関連業者さんたちは、デパートと提携したり、着物のレンタル事業に力を入れたりするなど、何とか生き残ろうと、大変な苦労を強いられた時代でもありました。
この頃から、着物のお手入れに関する「知識」や「技術」が、一般の家庭から失われていきました。多くの人が、「着物のお手入れって、どうすればいいの?」と分からなくなり、結果として、大切な着物がタンスの中で眠ったまま、シミやカビが生えてしまう、という悲しい状況も増えていったのです。これは、着物の物理的な劣化だけでなく、文化的な継承が途絶えてしまう危機でもありました。
クリーニング業界は「大躍進」、でも着物は「苦手」?
一方で、洋服を専門に扱うクリーニング業界は、この昭和の時代に、まるでロケットのように急成長を遂げました。「ドライクリーニング」や「ウェットクリーニング」といった、新しい洗濯技術がどんどん進化し、中には24時間いつでも受け付けてくれるお店や、家まで取りに来てくれる宅配サービスなども登場しました。私たちの洋服のクリーニングは、ますます便利になっていったのです。
しかし、残念ながら、これらの急成長したクリーニング店のほとんどは、着物の扱いに対応することが難しかったのです。一般的には「洋服専門」のままで、着物のお手入れサービスは縮小していく傾向にありました。
その背景には、いくつかの構造的な問題がありました。
- 着物に対する知識不足:着物の素材である絹は、水や特定の薬剤に非常に弱く、洋服とは全く違う専門知識が必要です。多くのクリーニング店は、その知識や経験が不足していました。
- 型崩れのリスクの高さ:着物は形が複雑で、洗い方によってはすぐに型崩れしてしまうリスクが高いため、非常に手間がかかります。
- 手間とコストに見合わない利益:着物のお手入れは、一枚一枚が手作業で、時間と技術が必要です。その割に、洋服のクリーニングに比べて依頼数が少ないため、お店にとってはあまり「儲けにならない」という現実がありました。
このような理由から、クリーニング業界全体として、「着物を扱いたがらない」という風潮が広まってしまったのです。これにより、着物の専門的なお手入れを受けられる場所は、さらに少なくなっていきました。
着物リフォーム・リユース市場の「意外な盛り上がり」
着物文化が衰退していく中で、面白いことに、「着物を解いて洋服や小物にリフォームする」という新しい流れが生まれ、注目されるようになりました。着物として着る機会は減っても、その美しい柄や上質な素材を活かしたいというニーズがあったのです。
着物の布(反物)としての価値が改めて見直され、着物を解いて帯やバッグ、コート、ワンピースなどに作り替える、「リメイク」の事例がどんどん増えていきました。
さらに、骨董市(こっとういち)やリサイクルショップで、古い着物が売買されるようになり、着物の「リユース」(再利用)文化が、ひっそりとではありますが、しっかりと成立していきました。これには、昭和後期に流行した「昭和レトロ」ブームや、昔の懐かしいものに郷愁(きょうしゅう:昔を懐かしむ気持ち)を抱く人々のニーズも影響していました。着物を「着る」だけでなく、「別の形で楽しむ」「再利用する」という、新しい着物の価値が生まれたのです。
この動きは、着物が単なる「過去の遺物」として忘れ去られるのではなく、形を変えて現代の生活の中に息づいていく、希望の光でもありました。洋服が主流になる中で、着物の持つ素材の良さや、職人の技術の高さが、リメイクという形で再評価されていったのです。
職人さんの技術を守る取り組みと、教育の強化
着物文化の衰退に危機感を持った多くの人々が、昭和の後期から平成時代にかけて、「この素晴らしい伝統技術を失ってはいけない!」と、動き始めます。地域の人々や、着物業界の団体が中心となって、「伝統技術を守る」ことを目的とした様々な取り組みがスタートしました。
染み抜き、洗い張り、染め替えといった、着物のお手入れに関する専門技術を学ぶための講習会が頻繁に開かれるようになり、専門学校でも、着物のお手入れや修復技術を専門的に学ぶコースが設置されるようになりました。
また、国の文化庁や地方自治体も、伝統的な技術を守るために「伝統工芸士(でんとうこうげいし)」や「無形文化財保持者(むけいぶんかざいほじしゃ)」(人間国宝など)といった認定制度を整え、大切な技術を受け継ぐ職人さんたちへの公的な支援を増やしていきました。これにより、これまで一人で技術を磨き、孤立しがちだった職人さんたちの「知恵の継承」や、「後継者(あとつぎ)の育成」に、一定の成果が見られるようになります。これは、日本の大切な文化が途絶えてしまうことを防ぐための、非常に重要な一歩でした。
このような地道な努力がなければ、今の時代に、これほど多くの着物職人の技術が残っていなかったかもしれません。「失ってはいけない」という強い思いが、新しい動きを生み出したのです。
まとめ:大量消費の時代だからこそ見えてきた、着物お手入れ文化の「本当の価値」
昭和の「大量消費」の時代は、着物とそのお手入れ文化にとって、確かに厳しい向かい風の時代でした。しかし、その一方で、着物を「リフォーム」したり「リユース」したりする市場が大きく広がったり、国や自治体、そして学校が協力して伝統技術を守るための取り組みを始めたりと、「伝統と再生」という、新しい可能性も同時に芽吹いた時期でもありました。
そして、この昭和の時代に築かれた、着物文化を守り、次へとつなぐための様々な活動が、その後の平成、そして令和の時代へと続いていく「着物文化の再興(さいこう)への土台」となった、と言えるでしょう。
着物は、ただの「古い服」ではありません。それは、「長く大切にする」という日本の美しい心、そして「物を再生させて活かす」という知恵を教えてくれる、生きた文化遺産なのです。昭和という激動の時代を経て、着物のお手入れ文化は、その真の価値を改めて私たちに示してくれました。